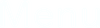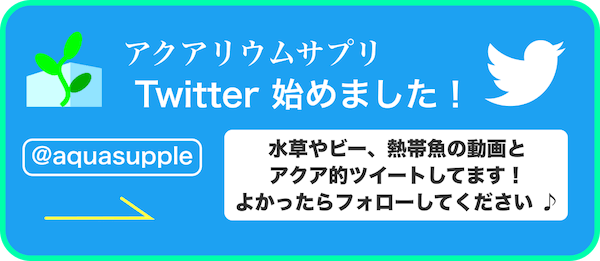水槽に大発生したアオミドロ(糸状コケ)の駆除対策!

とても幻想的なこの写真、アオミドロ(糸状コケ)の草原にミナミヌマエビ達が果敢に向かっている姿です。
「・・其の者、青き衣をまといて金色の野に降り立つべし・・」なんてナウシカの一節を彷彿とさせます。。
冗談はさておき、、
いや〜、本当に大発生しました。水槽に今までこれほど繁殖した事はなかったので、初めは戦々恐々です。

でもここで大事なのは、焦らず綿密に対応する事。焦って大きな間違い・失敗を重ねないようにします。
そして諦めない。意外と回復できるものですから。
今回は、繁殖しまくったアオミドロに対して効果があった駆除対策と私が行った改善までの手順について、実際に体験談を書いています。
もし同じようなアオミドロ被害に遭ってる方がいましたら、ご参考ください。
アオミドロ発生までの経過
当水槽は立ち上げから5年目ですが、実はこれまで大したコケ被害もなく無難に管理してきた水槽でした。
もちろん黒髭ゴケや茶ゴケが全く出ないわけではありません。それでも水草のための肥料は常に最低限をキープ、熱帯魚の餌も1日1回数分で食べ終わる程度、魚の数も水槽水量に対して余裕がある適量と、富栄養化を出来るだけ抑えたメンテナンスを続けていました。
ちなみに照明時間はずっと1日12時間(普通の27Wコンパクト蛍光灯)ですが、コケが悪化することはなくミナミヌマエビ達が掃除してくれる程度。
ヘアーグラスショート草原化計画から

それまでアヌビアスナナ・プチとロタラ類がほとんどで水草量も少なかったので、半年ほど前にヘアーグラスショートの草原化計画をスタートしました。

ヘアーグラスショートを新しく2束購入して植込み、それまでの照明に20Wスパイラル蛍光灯スタンドを追加、抑え気味にですが固形肥と液肥それぞれ肥料を増量します。

ここでもそれほど問題なく、順調にヘアグラスは繁殖していきます。
で、ついひと月ほど前、ミナミヌマエビの元気が落ちてるなとpHを測ると8以上になっていました。
これはミネラル肥料分の余剰蓄積だと考えて、硬度を下げる(pHを下げる)施策にクエン酸を使います。
この時点でもまだ、コケ被害はありません。クエン酸水の水換えも初めの数回は順調で、pHも徐々に下がりミナミヌマエビの調子も戻ります。
ちなみにクエン酸は、適量であれば生体はもちろん植物にも安全なものです。初めから生体内で使われてる成分ですから。“クエン酸回路”なんて理科の授業で教わったと思います。
ただここで、pHを弱酸性まで落とそうとさらに5回、6回とクエン酸水を繰り返したのが、たぶん問題だったと推測しています。
さらにその後思わず、大株に成長していたアヌビアスナナプチを5つほどに株分けします。
広く根を張って栄養を吸収していた株を抜いて分けたので、水草全体の栄養消費バランスが崩れたのもアオミドロ発生の原因となったはずです。これをきっかけにして爆発的に増殖しました。
考えられる問題点はこちら。
- クエン酸による金属イオンのキレート作用でミネラルが吸収しやすくなり富栄養化が起きた
- 草原化計画によって底床掃除がしづらくなり硝酸・リン酸の濃度が上がっていた
- 硬度の大きな変化によって水草の調子が落ちて富栄養化
- アヌビアスナナプチの株分けで水草全体の栄養消費量が低下
とにかく、pH調整に気を取られていた私は、若干アオミドロが発生していたのを知りながらヌマエビ任せに放置。その後数日で爆増しました。
まあたぶん、このバランスの崩れや富栄養化が収まらない事には、どんな先手を打ってもいずれ爆増したのではと思いますけど。
私の水槽環境とスペック
参考までに私の水槽環境(スペックなど)について書いておきます。
- 水槽サイズ:45cmショートスリム水槽(450×220×200)水量約20リットル
- 生体数:小型魚(4〜5センチ)×6匹、ミナミヌマエビ10匹前後(抱卵後不明)
- 水草:アヌビアスナナ・プチ、ロタラ、ヘアーグラスショート
- 底床:5年使用のゼオライト(ろか砂利)とソイル少々
- 照明:27W蛍光灯と20Wスパイラル蛍光灯スタンド(7時点灯19時消灯)
- 外部フィルター:エーハイム2005(2004からケース交換)
- CO2添加:半自動化した発酵式ペットボトル(7時30分から18時45分まで)
- 水温:26度オートヒーター
- 水槽pH:7.3前後
- 水道水pH:7.3〜8.0未満ほど(季節によって変動)
アオミドロ駆除対策の前に
有効と思われるアオミドロ駆除対策を複数同時に行っていますから、どれが正解と断定していません。
ただすべての工程を通して「富栄養化を抑える・排出・苔取り生体に食べてもらう」を前提に行いました。
アオミドロのあまりの勢いに焦って、軽率な行動に走らないように注意します。
1つ言える事は、アオミドロや緑ゴケが発生する水槽は、水草達にとってもそれほど悪くない環境です。熱帯魚やヌマエビなど生体だって居心地が悪いわけじゃありません。藍藻(らんそう)発生は別ですけど。
池や駆除農薬を使わない田んぼ等で見掛けたりしますが、アオミドロが繁殖する環境は微生物も増える良い環境なんですね。ただちょっと栄養素が過多なだけ。
確かに長期間そのままでは、アオミドロに隠れた水草の日照問題も徐々に出てきますけど、数日で駄目になるなんて事はありません。
私の場合でも、ヘアーグラスショートが約3週間アオミドロに覆われていましたが、特別大きな被害はありませんでした。
もちろん水草の種類によって違いはあるでしょうけど、どっしりと構えて、生体に悪影響が出ないように慎重に行っていきます。
ちなみに私の水槽ではアオミドロ大発生後、3週間から1ヶ月ほどで完治しました。
私が行ったアオミドロの駆除手段
ということで、ここからアオミドロ撃退のために私が行った駆除手段です。
肥料・トリートメント剤の添加を控える
まず富栄養化を促進してしまわないように、当然ですが肥料やトリートメント剤の添加をストップします。
このアオミドロ爆増は、まず栄養過剰な環境のはずです。
もしかしたら繊細な水草種は枯れてしまう可能性もありますが、アオミドロが抑制できない限り結局は同じ結末ですから、アオミドロ駆除を最優先します。
ちなみにこの水槽では、ヘアーグラスショートが最も肥料要求度が高い水草ですが、すべての水草にほぼ被害は出ませんでした。
ノーマルな水換えのみにする
水換えもごくノーマルなやり方のみに徹します。
水槽の3分の1から4分の1程度を塩素中和剤(カルキ抜き)のみで、その他の栄養分を添加せずに行います。
生体に影響が出るほど頻繁に換える必要はありませんが、高過ぎるリン酸や硝酸塩を排出する効果はありますから、「通常より多めかな」くらいの頻度で行います。
水槽と水道水のpH差が大きい場合は、ごくゆっくりと足し水します。
手で取れるアオミドロを排出
これも定番ですが、人為的に手(ピンセット)で取れるアオミドロを排出します。苔取り生体に全部食べてもらうより圧倒的に効率が良いですから。
ただし、大発生して初めのうちは無理してガツガツと取らず、水流に波打つ長い部分を中心に適度の排出に抑えておきます。
歯ブラシなどで擦り落とす方法も試してみましたが、やってみるとそれほど心地良くとれるものではありません。
とにかく、初めから綺麗に取り切ろうとは考えずに、下に隠れた水草を傷めない程度に優しく取れる分だけで大丈夫です。
今回の駆除経験で分かったのは、初期のアオミドロは勢いがあって水草にしっかり着床してますし、千切れづらい頑固さがあります。
ですが、富栄養化を抑えて行くとだんだん着床も弱くなり、細胞が衰えて千切れやすくなっていきます。
また、増えたアオミドロ自体も栄養を吸収してくれる存在ですから、富栄養化を早く抑える一端を担ってくれます。
充分に栄養を蓄えたアオミドロを撤去すれば、水槽内の過剰な栄養を分かりやすく排出する事になります。
ちなみにアオミドロの人為的な排出は、水換えと同時に行うと効率的です。
アオミドロを千切ると細かい切れ端が浮遊するので、それを飼育水と一緒に吸い出す要領です。
駆除してる時は一時的にフィルターを停止して流れを止めるとやりやすくなります。
また、過剰な栄養が減ってアオミドロが弱体化してきたら、チューブをそのままアオミドロに当てれば、スルスル抜けるように吸い出す事ができました。
(※止めたフィルターは忘れずに再稼働します!長時間、循環させないとフィルター内バクテリアが酸欠で死滅してしまいます。1時間程度なら問題ありません。)
二酸化炭素(CO2)を添加
水草育成に不可欠な光合成のため、二酸化炭素(CO2)は継続して添加します。照明点灯中のみ供給。
当然アオミドロも二酸化炭素を吸収して光合成しますが、そのためにアオミドロに覆われた水草のCO2不足が考えられます。
光合成はCO2の有無でも制限されてしまいますから、アオミドロにCO2を奪われて水草の成長が阻害されない対処と考えました。
またCO2添加で、無駄な茶ゴケの発生を抑える役割も加味します。
CO2供給をした事がない方には、安価に誰でもできる発酵式CO2ペットボトルがおすすめ。もちろん私もずっと発酵式ペットボトルを愛用しています。
(作り方の記事「水草の発酵式CO2添加装置をペットボトルで自作する作り方」もよろしければ後でご覧ください。)
照明光度の調整(?)
一般的に照明時間の長さや光の強さも、コケやアオミドロの増加に影響すると言われています。
ただ正直なところ照明光度に関しては、私は巷で騒がれるほど重要には捉えていません。
というのも自然光(日光)は、蛍光灯は元よりLEDなど照明器具では到底及ばない明るさがあります。メタハラや超ハイパワー照明でやっと3万ルクスくらいの薄暗い曇り空レベルですから。
真夏の直射日光で10万ルクス!
一般家庭でそんな高光量の設備環境を作ってる方は、まずいないでしょう。しかもそんなに高効率ハイパワー照明を水槽に当てたら、光の熱で水温上昇を抑えられなくなります。
もちろん、自然界の水草がどのような環境で育っているか、生息する水域の水の透明度や水深などの差異もあるでしょうが、市販で売られている多少強めの照明器具程度でその差異が完全に埋まるとも思えません。
コケが増える原因と考えるべきは、やはり余剰分の栄養素。
ソイルや水草肥料の栄養具合、生体の排泄するアンモニアなど有機物をコントロールすれば、一般常識になっている照明方法ほど過敏に意識しなくても良いのではと思っています。
そこで私はアオミドロ対策中ずっと、これまで通り12時間照明のままで行いました。
大発生するまでの半年ほども、27Wコンパクト蛍光灯と20Wスパイラル蛍光灯スタンドの2つを12時間点灯して、問題なく安定管理していましたから。
ただ、大量のアオミドロ初体験でちょっとビビリになっていた私は、追加で付けていたスタンド照明のみ外しました。。
まあ後々考えると、光量が強くてアオミドロ繁殖に加担したとしても、富栄養状態が低下してくれば不安定なアオミドロからまず弱っていくと思うので、やはり別に外さなくても良かったなと感じています。
とりあえず景観的に邪魔でしたし、どちらにしろヘアーグラスが全体的に生え揃ったら外す予定だったので、良しとします。(なんか言い訳っぽい。。汗)
照明の注意点として、生体はもちろん水草にも生体リズムがありますから、明るい時間と暗い時間は必ず必要です。
照明時間を12時間に決めたのも、生息する熱帯魚の多いアマゾン川流域の日照時間の年間平均から算出しました。
(水槽pHは反して弱アルカリ性ですけど。。)
で、アマゾン川の夜なんて街頭の全くない月明かりのみの世界ですから、真っ暗な状況をしっかり作ってあげるのも魚や水草の元気に繋がり、メンテナンスがより容易になります。
苔取り生体ヤマトヌマエビを追加
もともと水槽にはミナミヌマエビが抱卵して適度に増えていましたが、ミナミより格段に苔取り能力が高いヤマトヌマエビも2匹追加しました。
どちらかと言うと、ぶっちゃけこれも気休め的に増やした感じ。
ヤマトヌマエビはかなり食欲旺盛なため、水草の食害やミナミの稚エビを捕食してしまう恐れもあったので、今まで入れませんでした。
でも入れてみると案外かわいいものですね。
そしてたった2匹でも、多少はアオミドロの駆逐完了を早める手助けとなった実感があります。多く増やせばかなり駆除が早まったでしょう。
ただ過剰に増やした場合は、コケの減少後に水槽内を荒らさないように、ヤマトの空腹具合を見ながら適度に人工餌を沈める工夫も必要でしょう。
ちなみにアオミドロが無くなった現在の水槽では、まだ一度もエビに餌を与えた事はありません。それを考えたら入れ過ぎなくて良かったなと。
リン酸除去剤を外部フィルターに投入
アオミドロはリン酸過多で繁殖しやすいとも言われます。リン酸濃度を測定したことはありませんが、一度もリセットせず5年ほど経つ水槽なので、今回始めてリン酸除去剤を使ってみることにしました。
一つ言えるのは、アオミドロも水草と同じ植物ということ。
つまり窒素分やリン酸分を必ず必要とするわけで、増え過ぎてるリン酸を減らすのは間違いなく有効です。
使用法は難しくありません。フィルター内に追加投入するだけ。
ただし、あまりにもリン酸塩濃度が高い水槽で使うと急激にリン酸が減少して水質を変えてしまうという心配もありますから、その場合は繊細なエビなどに影響が出ないように、適度に水換えして慣らしてから設置すると良いかもしれません。
ちなみに私はすぐ投入したので、設置直後は熱帯魚が多少むず痒い仕草をしましたが、特段ヌマエビ達には影響ありませんでした。
マラカイトグリーンを添加
マラカイトグリーンは熱帯魚の白点病治療薬ですが、メチレンブルーと違って水草にも使える薬として非常に重宝します。そのマラカイトグリーンを1回添加し薬浴しました。
(※マラカイトグリーンに関しては、「アオミドロ駆除に薬浴」などと見聞きしたわけではないので、完全に私的な考察からの対処です。)
マラカイトグリーンは色素系の殺菌作用がありますが、病原菌の細胞に浸食・染色して遺伝子を傷付け攻撃します。そのため単細胞生物の細菌はもろにダメージを受けます。
でも熱帯魚や水草が影響を受けないのは、多細胞生物だから。細胞単位で多少ダメージを受けても細胞全体でみると影響がかなり微弱というわけです。
じゃあアオミドロはというと、多細胞生物ではありますが細胞数は少なく単調で、細胞が一つずつ一列に連なる貧弱な構造です。そのため魚やエビや大きい水草に比べて、遺伝子へのダメージが大きいのではと考えました。
確かにマラカイトグリーン薬はバクテリア環境にも影響を与えますが、実験的に1度だけ水量に対する規定量を添加。
白点病に対するマラカイトグリーンは、即効性というよりじわじわと効く印象ですし、数週間を目安に効果を期待します。必要以上に何度も行うのは問題ありそうなので、おすすめしませんが。
後もう一つ知っておきたい事。
マラカイトグリーンは人間に対しても発がん性が疑われる成分です。肌への浸透性があるので、手や目、口に飛散しないように注意して扱いましょう。
ちなみに、今回この薬を使ったことによるエビなど生体・水草への影響は、一切感じられませんでした。ミナミヌマエビやヤマトヌマエビも1匹も死ぬことなく、今も元気にツマツマしています。
アオミドロ撃退までの手順と経緯
アオミドロ撃退までの手順と、私の経緯を書いてみます。

これがアオミドロ爆増前の状態。
アヌビアスナナ・プチを株分けして植えた直後の写真で、赤い矢印の先、ヘアーグラスショートのところにアオミドロが少し絡まって生えていました。

ほんの一部分だけだったそのアオミドロも、富栄養な環境とナナプチの株分けをきっかけに数日で爆増。

「こんなに急に変わりますか?普通・・」というくらい一気に景色が変わりました。
色も青々として水流に揺らぐアオミドロ。。ミナミヌマエビもタジタジです。
そこでまず、わんさか増殖したアオミドロをピンセットで絡め取るように撤去しながら水換えします。

ですがまだまだ勢いのある初期アオミドロは、この程度ではびくともしません。翌日にはまた元通りに増えています。
それでも懲りずに10日間ほど掛けて、日を置きながら同じ作業を数回繰り返しました。
この段階では、手作業で撤去を何度繰り返しても時間が経つと元通り増殖しますから、無駄な作業に感じてしまいますが、多少でもアオミドロを減らすことで着実に余剰の栄養分を排出してますから無駄ではありません。
投げやりになって水草ごと抜いてしまわないよう、適度に取れる部分を無理せず撤去しました。

この作業を繰り返しながら、他の方法をじっくり考え、次にリン酸除去剤を外部フィルターに入れます。

(pHを変動させずにリン酸塩やケイ酸塩を強力に除去する評判のLIVESea(ライブシー)「フォストジュニアパック」を使用。)
そしてそれと同時期にヤマトヌマエビを2匹追加。
このリン酸塩除去剤とヤマト追加によって、若干勢いが収まった感じが見えてきます。とはいえ、まだまだゴールにはほど遠い印象。
それでも同じように、取れるアオミドロをピンセットで排除しながら水換えを続けます。
2週間過ぎた頃、マラカイトグリーン薬のヒコサンZを規定量添加。それから4日ほど薬浴のため水換えを控えます。

マラカイトグリーン後から徐々に、水換え時のアオミドロに貧弱さが感じられるようになります。むしった時にスッと切れる感覚や、エアチューブで直接吸い込むだけでボロボロと千切れる感じに。
これがマラカイトグリーンの効果なのか、それとも富栄養化が収まってきて栄養不足で弱体化したのかは分かりません。
ですがこれ以降は、ピンセットを使うよりエアチューブで水槽水ごとアオミドロを吸い出す方が効率が良くなっていきます。

(色も白っぽくなり始め、勝手に千切れるレベルに)
アオミドロの弱体化と同時に、ミナミヌマエビとヤマトヌマエビのコケ掃除能力がはっきりと感じられるようになり、目に見えてアオミドロ量が減り始めます。

(遠目に見た状態。水草にはまだ絡み付いていますが、水流に揺らぐほどのボリュームはもうありません。ちなみに、最初からずっと照明点灯中のCO2添加は続けています。写真左端のエアストーンから発酵式CO2供給。)
ここから急に展開が早くなり、残りがあと全盛期の半分くらいのボリューム(上の写真)から、ほんの3日間ほどでエビが平らげ、ほぼ消滅。
この頃にはもう増殖する力も無かったように思います。

葉の表面に残り1mmほど僅かに纏わり付いていたアオミドロ層も数日で完全に無くなり、駆除成功となりました。

現在はアオミドロの「ア」の字も見当たらないほど、大発生以前の状態に回復しています。
現在の状態。
一月ほど栄養を減らしての対策だったので、下葉(古葉)の黄化や葉枯れはありましたが、草体がダメになることはありませんでした。
肥料も再開して、ロタラ・ロトンディフォリアの赤みも戻ってきました。
アオミドロの経験と感想
一連のアオミドロ騒動の経験から思った事は、やはりアクアリウムは奥が深いなという感想。(爆)
面白い発見は、ネオンテトラやアルビノグローライトなど魚がアオミドロを啄ばむ様子が見れた事。立派な苔取り生体になってました。食べる量は少ないですけど。
そして、巷で言われる理屈や対処法が必ず正しいとは限らない事。
弱酸性から中性が飼育しやすいヌマエビだけど、この水槽では弱アルカリ性から下がった事がほとんどないですし、照明時間が長くても安定する環境が作れてます。
そりゃ水槽環境だって千差万別ですから、水槽それぞれで最短の正解は違って当たり前ですね。
ただ今回の経験でアオミドロ対策に最も効果的だったのはやっぱり、栄養素のコントロールでしょう。これは外せない。
肥料添加を止めて、手で駆除と水換えで栄養を排出。これが一番効いたと思います。

確かにヤマトヌマエビを20匹も30匹も入れれば、すべて食べ切ってくれるかもしれません。でも、その後エビ達どうするのという。
水草の食害、排泄物の増加から茶ゴケや黒髭コケの増加、食の取り合いや共食い、魚への危害など、生体が増えれば違う問題が出てくるかもしれません。
これも言ってしまえば栄養素コントロールの一部な気がします。
アオミドロやコケ対策に3日間ほど遮光する方法も良く聞きますが、これ、富栄養化に対して何の進展もないですよね。コケが衰退しても水槽内の栄養量は変わらない。
逆に光を遮る事で同時に水草の調子も悪くして栄養消費のバランスを狂わす、再発する等、その先に良い結果が予測できませんでした。
いや、遮光対策で最大のネックは、3日間も水槽が観察できないことが我慢できない。。
ちなみに、pHを下げるとアオミドロが弱るという説は何となく納得。水槽の軟水化で栄養(カリウムなどミネラル分)を減らす効果がありそうです。
ただ、pHを大きく変えるのは生体に影響が出やすいので、かなり注意が必要です。
今回の私の水槽は、水道水の影響でずっとpH7.5近くでしたから、アオミドロ対策のために無理してpHを酸性に傾ける必要はないはずです。
問題有りはオキシドール(過酸化水素水)。
アオミドロに直接吹きかけると白化して弱るのですが、特にエビなど他の生体に悪い影響大です。
水量の多い水槽なら多少は大丈夫ですけど、水量の少ないミニ水槽ではやらないのが得策です。正直、オキシドールは何日も続けて行わないと効果が現れにくいので、生体へのストレスが強過ぎるところがあります。
そこでマラカイトグリーンでした。
今までも治療で数回使った経験はありますが、1度使う程度ならヌマエビに影響が出たことはありません。とはいえ今回のアオミドロ弱体化がマラカイトグリーンの効果なのか低栄養になったお陰なのか、はっきり分かりませんでした。
無闇に薬を使う事に抵抗がある方も多いでしょうし、まずは根気よく手で駆除と水換え、そしてちょっとエビの力を借りる手段がおすすめです。
アオミドロ対策の参考リンク
[PR]

リン酸除去剤 デルフィス LIVESeaフォストJr.パック 40g 用品・器具 水質管理関連 コケ抑制剤
デルフィス「ライブシーフォストJrパック」はpHを変えずにリン酸塩を除去できます。
パック入りでそのままフィルターに入れるだけで簡単。
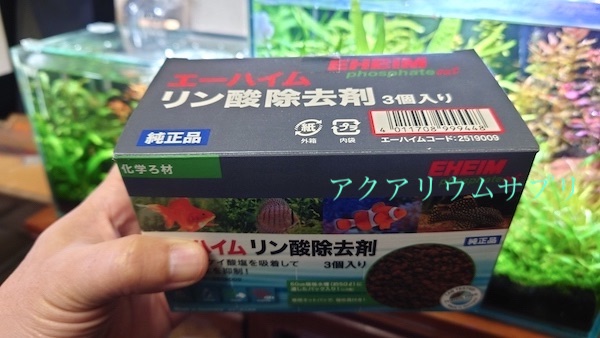
エーハイムのリン酸除去剤も安心して使えます。
[PR]

エーハイム リン酸除去剤 (3個入り) 淡水・海水用
それと熱帯魚飼育に常備しておきたい魚病薬。
[PR]

(魚病薬)マラカイトグリーン液 ヒコサンZ 80ml 計量カップ付き 熱帯魚 金魚 白点病 尾腐れ病 水カビ病 熱帯魚・アクアリウム
そうそう使うものではないですが、いざという時に「ヒコサンZ」はあると便利。
マラカイトグリーン液は「ヒコサンZ」か「アグテン」が有名です。どちらもほぼ同じです。
ホームセンター熱帯魚コーナーにはどちらか置いてると思います。
お子さんのいるご家庭は手の届かないところに。
各種コケと具体的な対処法!

⇒「水槽のコケ対策は環境からが基本!」こちら
水槽環境の安定化!人気記事

⇒「水換えの要らない水槽は可能!方法と真実を解説」こちら
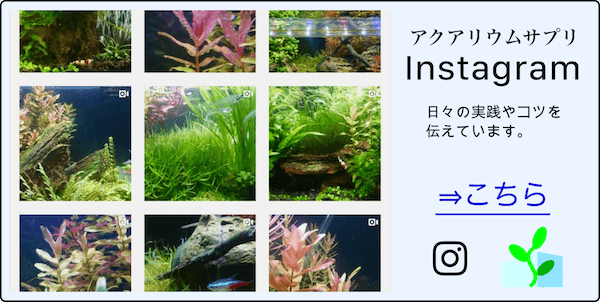
スポンサーリンク